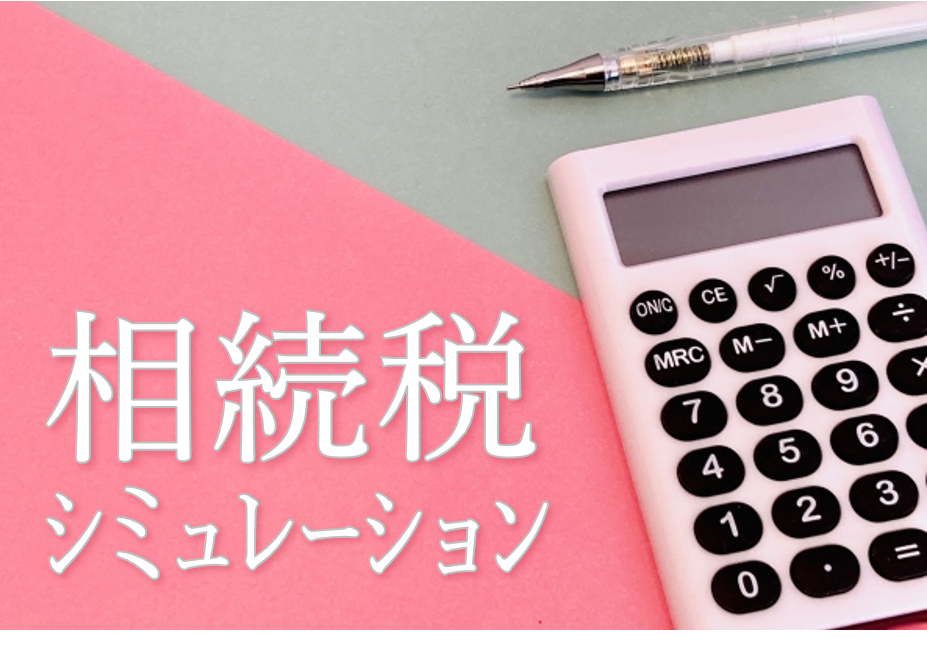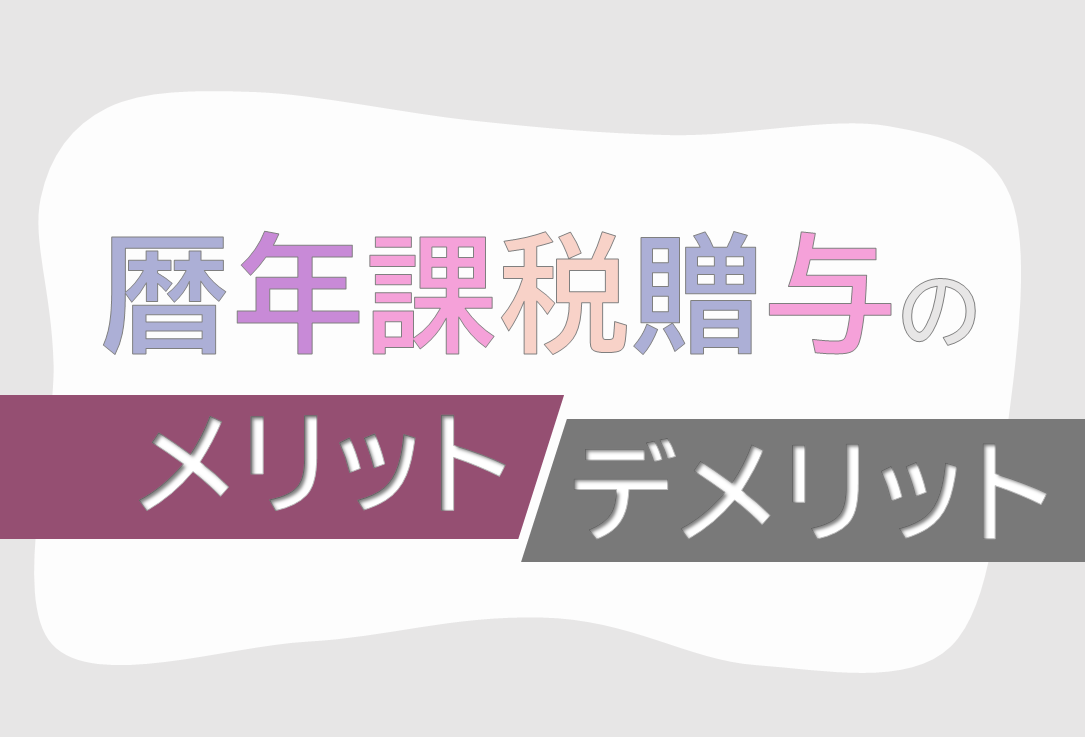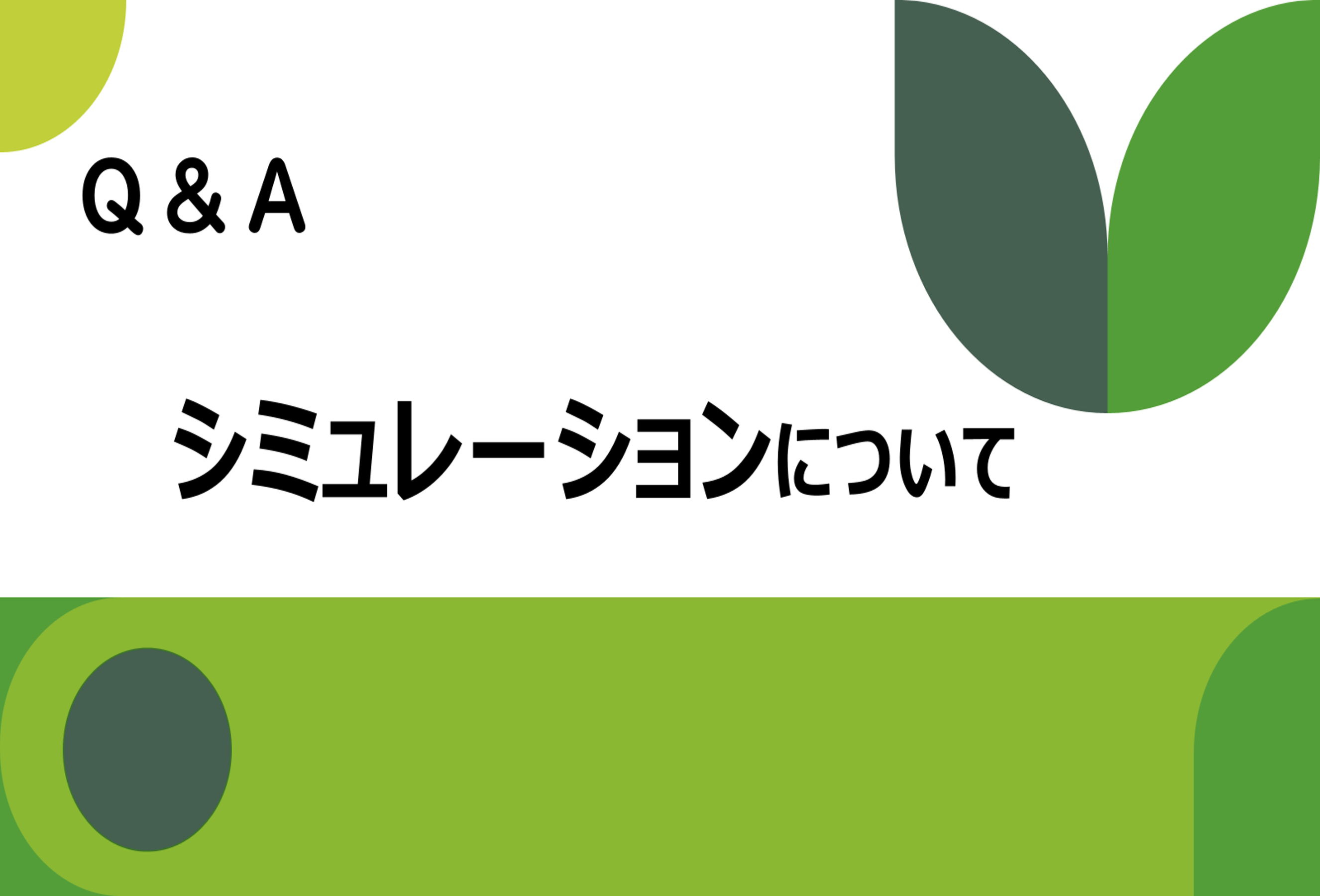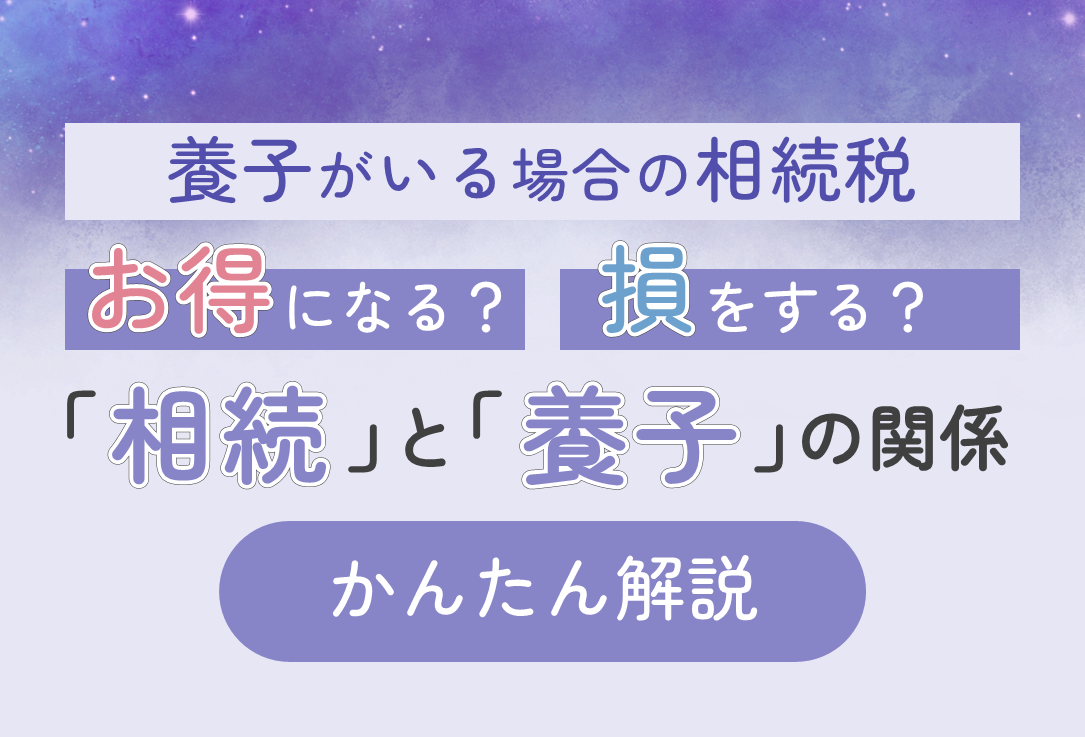【今年の準確定申告は要注意】提出日によって税額が変わります~令和7年度税制改正による影響~

はじめに|
この記事が必要となる方は、本年中にご家族を亡くし、令和7年(2025年)11月30日以前に準確定申告の手続きが必要となる方です。
現在、ご家族を亡くされた悲しみの中で、今は何から手をつけて良いのか分からない——
心が安堵する間もなく役所や会社から届く書類、年金や保険、そして「税金」や「年末調整」に関する手続き・・・。
見慣れない書類や申請に頭を悩まされているか、それらが落ち着いて少し休める状況になった頃かと思います。

令和7年(2025年)は国の税制が大きく変わる「節目の年」にあたり、この年に限って注意が必要なポイントがいくつかあります。
たとえば、
令和7年12月1日より前に亡くなった場合、
今年から適用されるはずだった「控除の拡大」などの優遇措置が適用されません。
つまり、本来であれば返ってきたかもしれない税金が戻ってこないというケースがあるのです。
こうした情報は、一般の方には非常に分かりにくく、また、説明もされにくいのが現実です。
そこで、このコラムでは、令和7年にご家族を亡くされた遺族の方が、税金や年末調整について何を知っておくべきか、どう対応すればよいのかを、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
ご自身のペースでゆっくり読んでいただけましたら幸いです。
1|令和7年の税制改正で何が変わったのか
令和7年は、国の税金の仕組みに大きな変更がありました。
| 改正内容 | 一般的な影響 |
| 基礎控除の引き上げ | 多くの方が該当する控除が引き上げられました。 特に、収入が少ない方の税負担が軽くなるように変更されました。 |
| 扶養家族の収入上限引上げ | 配偶者やお子さまなど、扶養に入れる収入上限が引上げられました。 |
| 特定親族特別控除の新設 | 大学生などの子どもがアルバイトなどで稼ぐことができる収入上限が引き上がりました。 |
本来であれば、この改正は令和7年の12月1日より施行されるため、以降に年末調整をすることで対象の方は税金が戻ってくる(還付される)のですが——
亡くなった方の場合には、少し事情が変わってきます。
2|もし、新制度が施行される12月1日「より前」に亡くなった場合
前述した通り、令和7年度の税制改正は、≪令和7年12月1日から施行≫です。
そのため、
ご家族が12月1日より前に亡くなられた場合、今回の税制改正(控除の増額など)は適用されません。
年末調整はその年の12月31日時点で在職している人が対象ですので、亡くなった方には実施されません。
その代わりに、「準確定申告」を行う必要があります。
3|「準確定申告」とは?
準確定申告は、亡くなった方に代わりご家族(相続人)が税金の精算(確定申告)を行います。
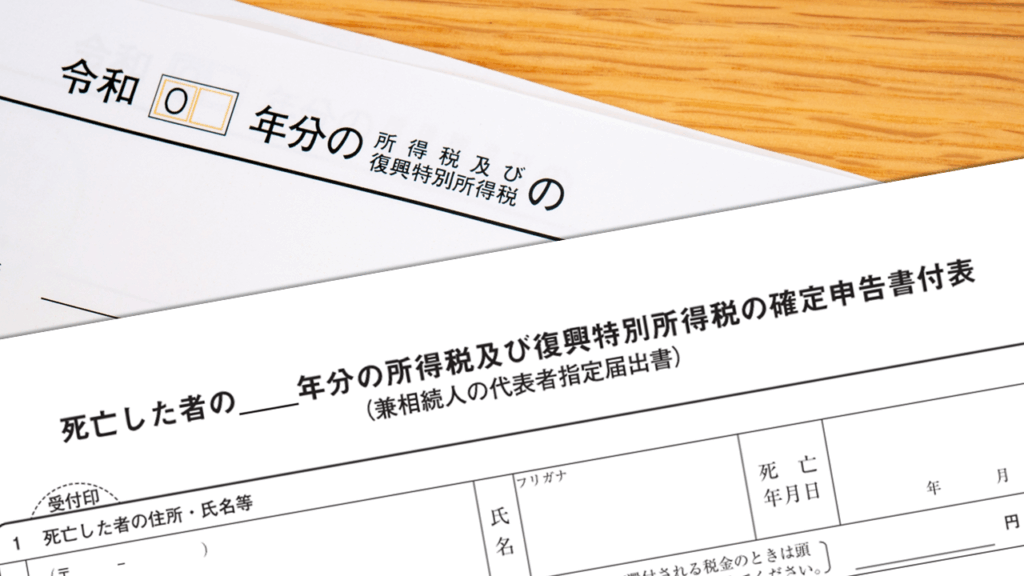
準確定申告が必要になるのは、主に以下の場合です。
- 亡くなった方が源泉徴収や予定納税など、なんらかの形で税金を納めている場合
- 亡くなった方が生前に確定申告をしていた場合
- 亡くなった年に保険金の受取や、不動産の売却を行った場合
準確定申告の期限は通常の確定申告時期(3月中旬)とは異なり、被相続人の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から「4か月以内」です。期限を過ぎた場合、加算税や延滞税がかかることもありますので注意が必要です。
4|令和7年改正と混乱しやすいポイント
税制が変わったとはいえ、その内容が亡くなった時期によって適用されるかが異なるため、次のような混乱が起きやすくなります。
| よくある疑問 | 実際は… |
| 「今年は控除が増えたと聞いたのに、なぜ税金が戻らないの?」 | 12月1日以降に準確定申告、または更正の請求が必要です |
| 「子どもが大学生なので、特別控除を使えるのでは?」 | 12月1日以降に準確定申告、または更正の請求が必要です |
| 「年末調整がされていないと言われたが、どうすればいい?」 | 準確定申告が必要です。期日(4カ月以内)までに申告することと、期日が12月1日より前の場合は、更正の請求も検討しておきましょう。 |
【令和7年分の注意点まとめ】
- 令和7年度の改正は12月1日以降に施行される。
- 亡くなった方の税金の精算は「準確定申告」を行う。
- 準確定申告の期日が令和7年11月30日以前の場合、新制度を適用させたい場合は12月1日以降に「更正の請求」を行う。
改正が施行される日以前に準確定申告を行った場合、従来のルール(令和6年までの税制)に基づいて税金の手続きが行われることになり、改正内容は適用されません。
改正内容を適用したい場合は、令和7年12月1日以降に「更正の請求」が必要となります。
更正の請求は5年間遡ることができますので、令和7年12月1日から令和12年12月2日(※1日が日曜日のため、税務署の次の開庁日)まで請求することができます。
最後に|
大切なご家族を失われたお気持ち、どれほどお辛いかと拝察いたします。
私ども税理士がご遺族の方のお力になれるとしたら、一般の方にはわかりにくい税制についてわかりやすく情報提供し、亡くなった方が最後に働いた証としてきちんと税額を精算・納税していただくようお手伝いすること。
煩雑な作業ではありますが、故人の人生の締め括りに関わる大切な手続きでもあります。
相続手続きや準確定申告について、少しでもお悩みがあれば専門家にご相談ください。
この記事を書いたのは
京都・相続遺言相談所(法人名:新経営サービス清水税理士法人)
新経営サービス清水税理士法人の相続・遺言専門のプロが集う。女性税理士を筆頭に、「お客様に安心と信頼を!」をモットーとし、きめ細やかなサポートに定評がある。事業承継プロジェクト発足以来25年以上の歴史があり、年間100件近い申告と相談を受けている。母体である新経営サービス清水税理士法人のグループ会社には、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所があり、相続税の申告から不動産の名義変更まで、ワンストップで受注可能。