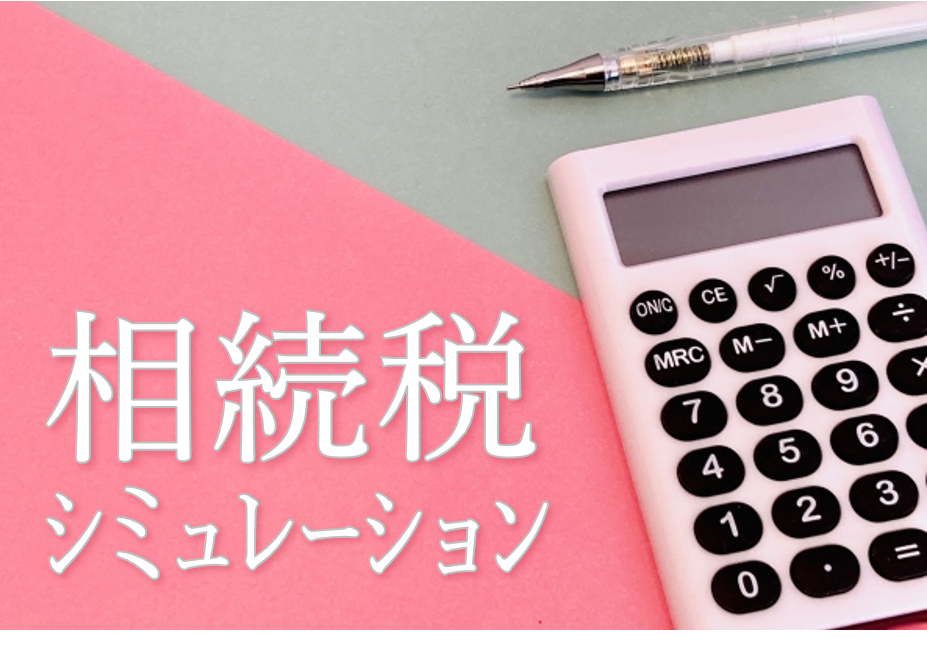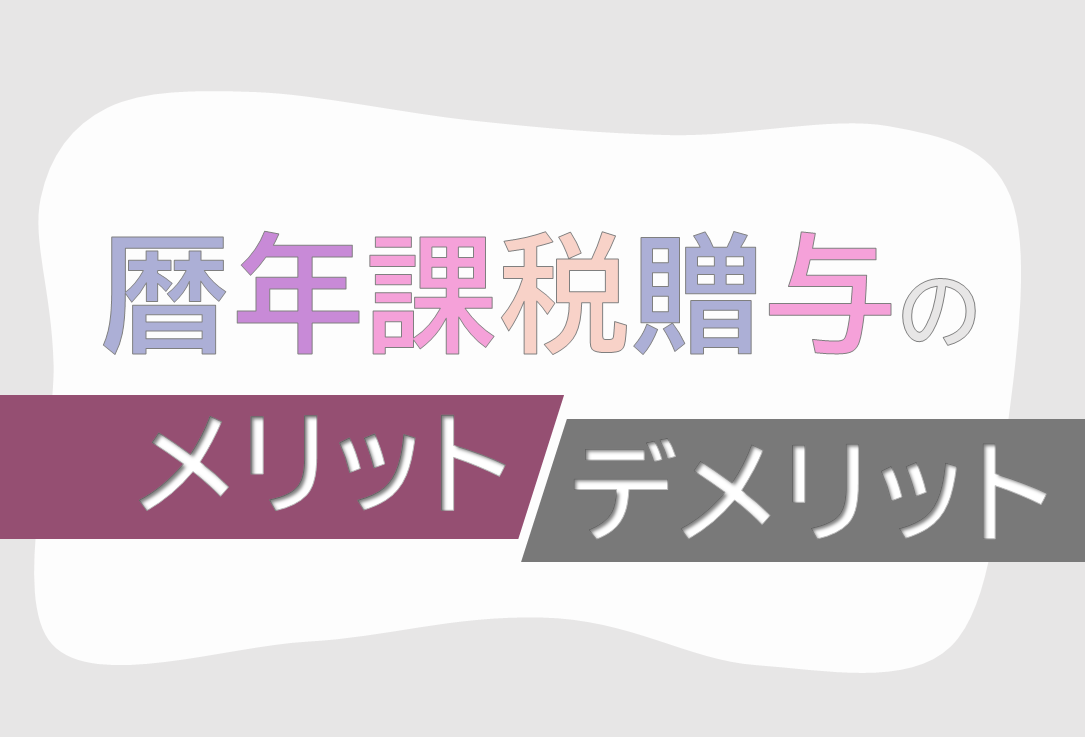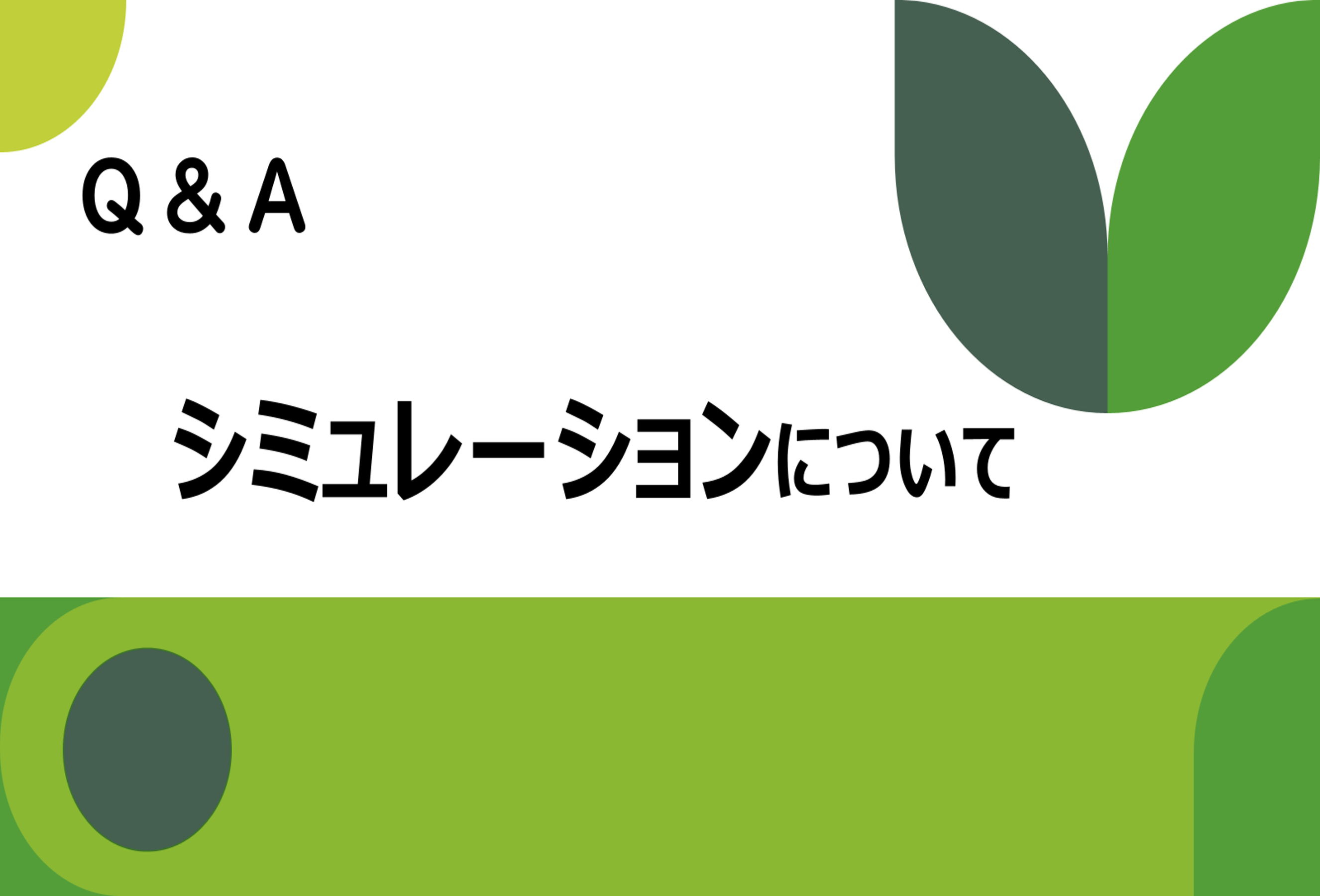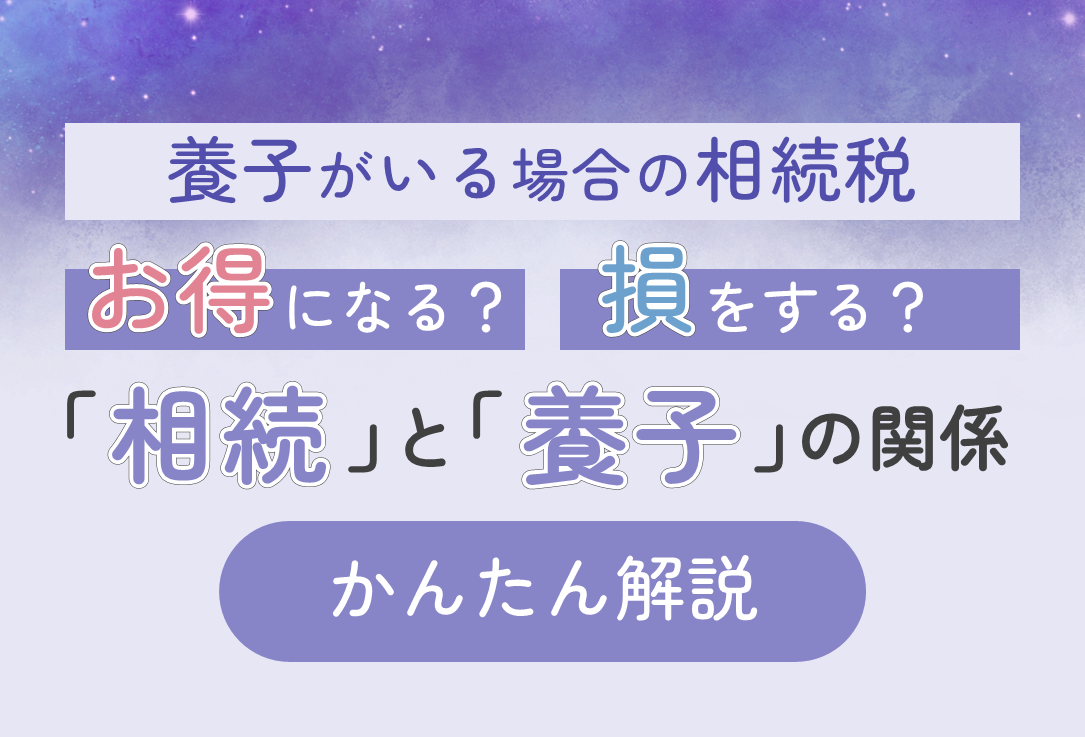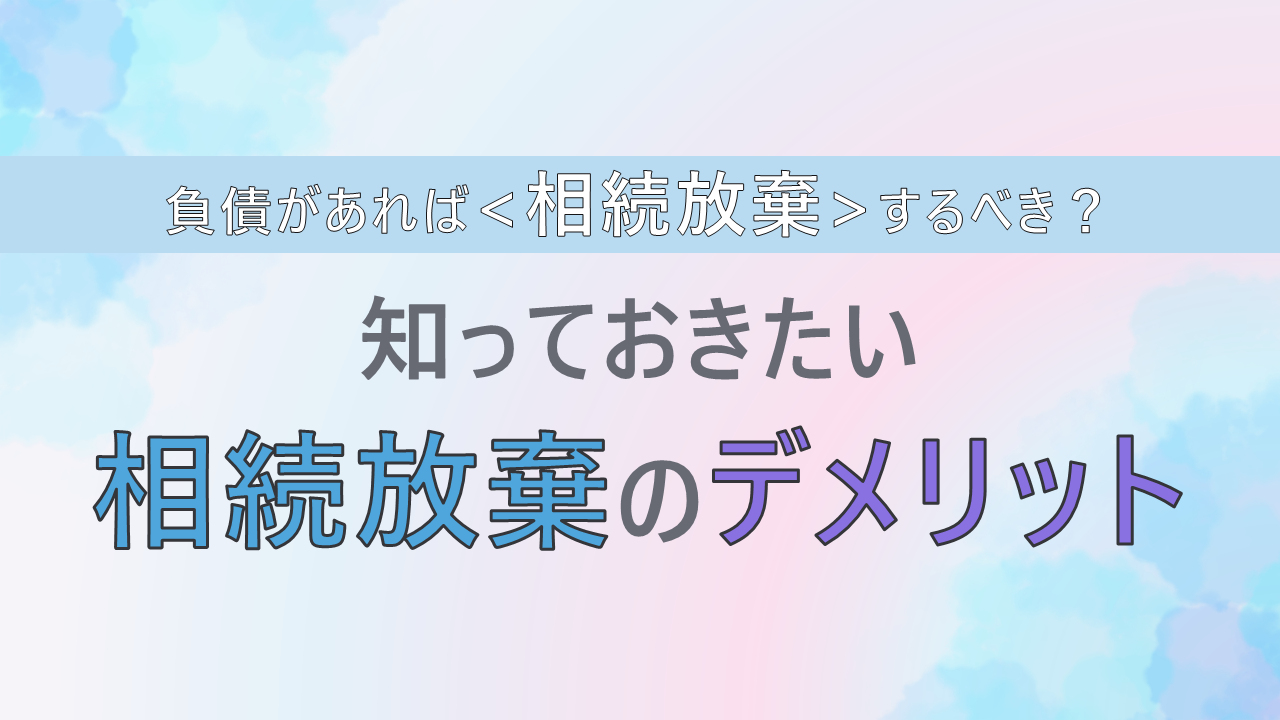<相続税対策は生前から>税理士が教える5つの節税ポイント

「うちは相続税がかかるのかな?」
「相続税対策なんて、実際に相続が発生してみないとわからないよね」
実は、相続が発生してから相続税対策をしても間に合わないことが多いのが現実です。
特に不動産や金融資産を多くお持ちのご家庭では、「思ったより税額が高かった・・・」「もっと早く相談していれば・・・」という声もよくお伺いします。
この記事では、誰でも利用しやすい「生前からできる節税対策」を5つにまとめてご紹介します。
「相続税が心配だけど、生前に何をしておけばよいのか分からない!」という方は、ぜひご一読ください。
❶ 毎年の「暦年贈与」を活用する

最も基本的な対策が、「贈与税の基礎控除」を活用する方法です。
🎁 贈与税の基礎控除まとめ
- 非課税額:年間 110万円
- 対象者:1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた人
- 贈与者が誰であっても合算される
📌 例:
- 親から:80万円
- 祖父母から:50万円
合計:130万円
控除後:130万円 − 110万円 = 20万円に課税される
こんな方におすすめ:
- 子どもや孫がたくさんいる方
- 預金が多く、相続税の対象になりそうな方
通帳・印鑑は贈与された人が管理すること。
名義預金とみなされると、相続税の対象になる可能性があります。
❷ 不動産を活用して評価額を下げる

現金よりも不動産の方が相続税の計算に用いられる評価額が低くなる傾向があります。
例えば同じ3,000万円でも、現金は額面そのままが評価額となりますが、土地や建物の場合は路線価や固定資産税の評価によって評価額が異なります。
中でも賃貸アパートの場合、「自由に使えない土地や建物」とみなされて土地の評価が低くなり、相続税も軽くなる可能性があります。また、小規模宅地等の特例(賃貸アパートの場合、50%減額)が適用できると、大幅な節税が可能です。
ただし、無理に不動産を買って節税しようとすると、将来のトラブルや維持費の問題も。
また、購入した時期によっては小規模宅地等の特例が使えないケースもあるため、注意が必要です。
不動産購入を検討される際は、一度専門家にご相談を。
❸ 生命保険を活用する

相続人が受け取る死亡保険金には、相続人1人につき500万円の非課税枠が適用されます。
相続人が配偶者+子2人=3人の場合 → 1,500万円まで非課税!
また、死亡保険金は「現金で受け取れる財産」なので、納税資金としても有効です。
保険の種類によっては、老後資金との両立も可能です。
❹ 家族信託・贈与信託で「資産を渡す」「管理する」

近年注目されているのが「家族信託」や「教育資金の一括贈与信託」です。
家族信託:
- 認知症対策や事業承継に有効
- 財産を信頼できる家族に託して、管理・処分を任せる仕組み
教育資金贈与信託:
- 1,500万円まで非課税で贈与可能(一定要件あり)
- 孫の教育費として使う場合などにおすすめ
制度の要件や税制改正の影響を受けることがあるので、専門家によるサポートが必要です。
❺ 遺言書+相続税試算で「争族」と「節税」の両方を対策
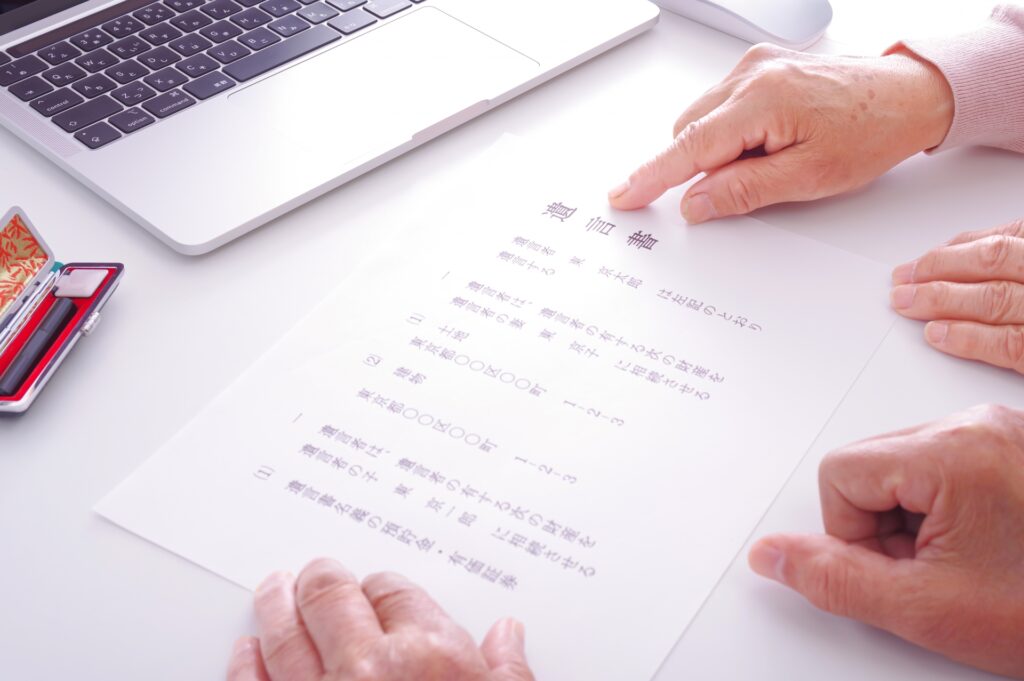
相続税の節税だけでなく、「相続人同士が揉めないようにする」ことも、生前対策として大切です。
- 遺言書を作っておくことで、分割トラブルの防止に!
- 相続税のシミュレーションを事前にしておくことで、納税資金や分割の方針も見えてくる!
「節税」と「円満な相続」は、どちらも本人の意思を尊重しやすい生前の準備が決め手です。
まとめ|相続税対策は、思い立った「今」がベストタイミング‼

相続税の節税は、「亡くなってから」では手遅れになるかもしれません。
今、ご自身の意思で少しずつ準備しておくことで、大切な家族の負担を大きく減らすことができます。
- 贈与を始めたいけど、方法が分からない
- 相続税がかかるか、まず確認したい
- 具体的な相続税対策を知りたい
相続対策についてお悩みの際は、ぜひ一度、「京都相続遺言相談所」にご相談ください。
この記事を書いたのは
京都・相続遺言相談所(法人名:新経営サービス清水税理士法人)
新経営サービス清水税理士法人の相続・遺言専門のプロが集う。女性税理士を筆頭に、「お客様に安心と信頼を!」をモットーとし、きめ細やかなサポートに定評がある。事業承継プロジェクト発足以来25年以上の歴史があり、年間100件近い申告と相談を受けている。母体である新経営サービス清水税理士法人のグループ会社には、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所があり、相続税の申告から不動産の名義変更まで、ワンストップで受注可能。